家族葬とは-まとめ
 近年、家族葬が広く普及し、特にコロナ禍以降、その需要が高まっています。しかし、家族葬について十分に理解せずに進めると、思わぬ費用がかかることがあります。ここでは、家族葬の特徴や意義について詳しく解説します。
近年、家族葬が広く普及し、特にコロナ禍以降、その需要が高まっています。しかし、家族葬について十分に理解せずに進めると、思わぬ費用がかかることがあります。ここでは、家族葬の特徴や意義について詳しく解説します。
家族葬の由来と密葬との違い
家族葬とは、その名の通り、家族や親しい親族のみで執り行う葬儀のことです。規模としては「密葬」に近いですが、密葬はその後に一般の参列者を迎える「お別れ会」などを行う点が大きく異なります。
葬儀に対するニーズの変化
昭和から平成にかけては、通夜と告別式を行う「一般葬」が主流でした。しかし、寿命の延びに伴い、故人の社会的な関わりが減少し、参列者の数も少なくなる傾向が強まりました。また、参列する側も高齢化が進み、移動が困難になるケースが増えています。
こうした背景から、近しい親族のみで行う「家族葬」が一般葬の縮小版として生まれました。さらに、コロナ禍による参列制限が追い風となり、現在では家族葬が一般的な葬儀のスタイルになりつつあります。
家族葬の特徴
家族葬は、一般葬の規模を小さくしたもので、基本的には通夜・告別式を行います。しかし、従来の大規模な葬儀ホールは費用が高く、少人数の葬儀には適していませんでした。そこで、少人数向けの家族葬専用ホールが登場し、20名程度までの参列者を想定した小規模な施設が増えています。
また、祭壇や供花の規模も抑えられ、費用を軽減できる点も特徴です。こうして、家族葬は次第に一般化していきました。
通夜を省略する「一日葬」の普及
家族葬では、元々告別式のみを行うため、通夜を省略する「一日葬」が主流となっています。一日葬にすることで、遺族の負担を軽減し、費用も抑えられるというメリットがあります。
なお、親しい友人などの参列も可能なため、二日葬(従来の通夜・告別式)を行う必要性が低くなっています。これも、現代の葬儀のニーズに合った変化といえるでしょう。
無宗教葬の増加
現代日本では、宗教に対する信仰心が薄れ、宗教に縛られない「無宗教葬」を選ぶ人が増えています。無宗教葬では、仏教葬儀のような読経や戒名の授与を行わず、宗教的な要素を省いた形で葬儀が進められます。そのため、費用の削減にもつながります。
また、歴史的背景として、かつて神道と仏教が混在していた時期がありましたが、明治政府による神仏分離政策を経て、信仰の多様化が進みました。現代では「成仏」の概念や神棚の習慣が残る一方で、特定の宗教を持たない人が増えています。
無宗教葬では、戒名費用や檀家制度の負担が不要になり、寺院との関係を持たない形で葬儀を行えます。そのため、墓じまいや離檀を考える家庭が増えたことも、無宗教葬の選択を後押ししています。葬儀の進行は一般的な家族葬とほぼ同じですが、宗教的な要素がない点が大きな違いです。
火葬式(直葬に近い形式)
火葬式は、告別式を行わず、棺への花入れや短時間のお別れをするだけの形式です。場合によっては焼香台を設置し、焼香を行うこともありますが、従来の葬儀とは異なり、簡素な儀式となります。
火葬式は、10名以内の参列が適当とされ、それ以上の人数になる場合は告別式を行うほうが適しています。火葬場にお別れの部屋が用意されていることもあり、そこで最後の時間を過ごすことが可能です。祭壇費用がかからないため、一日葬よりも大幅に費用を抑えられます。
直葬(火葬のみ)
直葬は、火葬式よりもさらに簡素な形式で、通夜・告別式を一切行わず、火葬のみを行う葬儀です。故人の安置場所から直接火葬場へ移動し、短時間での別れを済ませます。
一部の葬儀社では、火葬前に短時間の花入れや副葬品の納棺を許可している場合もあります。費用は最も安価で、一般的に10万円台で収まることが多いです。
家族葬のメリットとデメリット
メリット
遺族の負担軽減
参列者対応の負担が少なく、遺族が落ち着いて故人と向き合う時間を持てます。
費用の削減
一般葬に比べて規模が小さいため、式場費や供花、飲食接待費などを抑えられます。
参列者への配慮
一日葬の場合、参列者も一日のみの参加で済むため、負担が軽減されます。
デメリット
故人の友人・知人への対応
基本的に親族のみで行うため、故人と親しかった友人や会社関係者が参列できないケースがあります。そのため、事前に周囲へ説明し、理解を得ることが重要です。
まとめ
家族葬は、今後さらに普及していくと考えられます。基本的な流れは一般葬と変わりませんが、規模が小さいことや、喪主の意向によって内容が異なることが特徴です。
特に注意すべき点は、家族葬と密葬の違いを正しく理解することです。それぞれの葬儀形式には、遺族や参列者の意向が反映されるため、その意向を尊重し、適切な形で進めることが大切です。


 ご葬儀
ご葬儀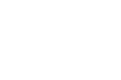 家族葬
家族葬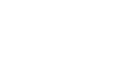 事前相談
事前相談